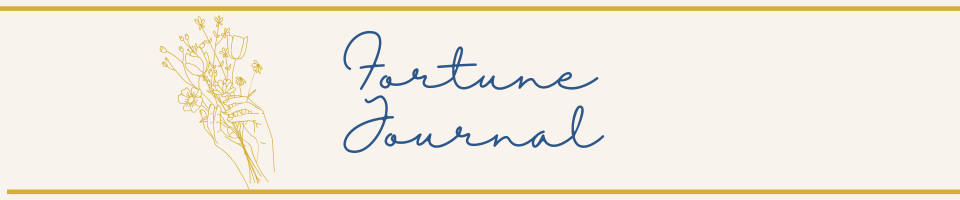「INFJって言われたけど、なんだか違和感がある…」
「何度やってもタイプが変わる」
「当たってるような、当たってないような…」
MBTI診断はSNSや占い界隈でも人気がありますが、その結果に「しっくりこない」と感じたことはありませんか?
そのモヤモヤの原因は、実はMBTIと心理機能診断の違いにあります。
この記事では、「MBTI」と「心理機能診断」がなぜ違う結果になるのか、どう使い分ければ納得できる自己理解につながるのかを解説していきます。
MBTIとは?簡単におさらい
MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)は、アメリカの心理学者ブリッグス母娘がユング心理学をもとに開発した性格タイプ診断です。
人間の性格を以下の4つの指標で分類し、16タイプに分けます。
MBTIの4つの指標(軸)
- 外向(E)/内向(I)
- 感覚(S)/直観(N)
- 思考(T)/感情(F)
- 判断(J)/知覚(P)
たとえば「ENFP」というタイプは、外向的・直観型・感情型・知覚型という意味になります。
MBTIは、質問に答えることで自分がどの指標に属しているかを判定してくれるシステムです。
「心理機能診断」って何?MBTIとの違いとは?
心理機能診断は、MBTIの基礎となったユングの「心理機能理論」をより本格的に応用した診断手法です。
ユング心理学による8つの心理機能
- 外向的感覚(Se)
- 内向的感覚(Si)
- 外向的直観(Ne)
- 内向的直観(Ni)
- 外向的思考(Te)
- 内向的思考(Ti)
- 外向的感情(Fe)
- 内向的感情(Fi)
MBTIでは4文字で性格タイプを表現しますが、心理機能診断は「どの機能を主に使っているのか」「その機能の順番はどうなっているのか」という、より詳細な心理構造を重視します。
同じINFPタイプでも、直観を多く使う人と感情を中心にしている人とでは、性格や行動に大きな違いが生まれます。
この深掘りができるのが心理機能診断です。
MBTIがしっくりこない理由3つ
1. MBTIは行動傾向の分類にすぎない
MBTIは性格の「傾向」を知るのに便利ですが、「なぜそのような傾向があるのか」という内面的な理由までは見ません。
行動の結果だけを見るため、根本的な動機や心理機能の働きが反映されないことがあります。
心理機能診断では、意識的にも無意識的にもどの機能をよく使っているかを分析します。
MBTI(エムビーティーアイ:Myers-Briggs Type Indicator)は、個人をタイプに分類したり、性格を診断したりすることが目的ではありません。回答した個人一人ひとりが、MBTI有資格者の支援のもと、自然としている自分の認知スタイルを分析しながら理解を深め、自分の心の成熟のためと自分と異なる人間への許容度を高めるための羅針盤となることを最大の目的にしています。
2. 回答の気分や環境で結果が変わりやすい
MBTIの質問は、自分がどう思うか、どう振る舞っているかに答える形式です。
そのため、その日の気分や状況、人間関係の影響などに左右され、診断結果がブレやすいのが難点です。
心理機能診断は、思考パターンや情報の処理方法を深く見ていくため、より安定した診断結果が出やすいのが特徴です。
3. J/Pの違いによる誤診断が多い
MBTIでは、「判断型(J)」と「知覚型(P)」の違いによって、表に出る機能が変わります。
しかしこのJ/Pの区別は曖昧になりがちで、ここで誤診断が起きやすくなります。
たとえば「INFJ」と診断されたけれど、実際には「INFP」だったというケースも珍しくありません。
その違和感を解消してくれるのが心理機能診断なのです。
自分に合った診断をするためのステップ
ステップ1:MBTIと心理機能診断を両方受ける
MBTIは手軽に受けられる反面、やや大雑把な分類になることも。
その後で心理機能診断を受けて、自分の使っている心理機能を確認することで、より納得のいく自己理解が可能になります。
ステップ2:主機能と補助機能に注目する
心理機能診断では、「主機能(最も使う機能)」と「補助機能(サポートする機能)」のバランスが重要です。
主機能がFi(内向的感情)なら、自分の価値観に従って行動する傾向があります。
補助機能がNe(外向的直観)なら、常に新しい可能性を探っているタイプです。
このように、自分がどの機能をどう使っているかを知ることが、より的確な自己理解につながります。
ステップ3:診断結果は「型」ではなく「ヒント」として活用する
「自分はINFPだからこうなんだ」と決めつけてしまうと、かえって自己理解を妨げることもあります。
診断結果はあくまでヒント。
心理機能を知ることで、自分が自然に選びやすい思考・行動パターンを把握し、日常生活や人間関係に活かすことができます。
実際にあった事例紹介
心理機能診断を受けたことで、「自分らしさは“外向的に見せる”ことではなく、“内面の価値観を守る”ことだった」と気づけた。
心理機能診断をもっと活かすために
- 診断は目的ではなく、「自分を知るツール」として活用する
- 対人関係でつまずいたときは、自分と相手の使う心理機能の違いを考えてみる
- 占いや風水と組み合わせることで、自分に合った開運方法も見えてくる
まとめ:違和感の正体は「心理機能」にあった
MBTIで「しっくりこない」と感じるのは、単にタイプが間違っていたからではありません。
その背後にある心理機能に注目することで、自分自身への理解が格段に深まります。
MBTIは性格の表面的な分類、心理機能診断はその根底にある心の動き。
この2つを組み合わせれば、「なぜ自分はこう感じるのか」「どんな選択をすれば心地よいのか」が明確になり、人生全体に役立てることができます。
次の一歩
- MBTI診断の結果にモヤモヤを感じた人は、ぜひ心理機能診断を試してみてください。
- 自分が何を大切にしているのか、どういう思考パターンを持っているのかを知ることは、仕事・恋愛・人間関係すべてに影響を与えます。
- 占いや風水が好きな方なら、心理機能診断と組み合わせて「本当に自分に合った運気アップ法」を探すのもおすすめです。