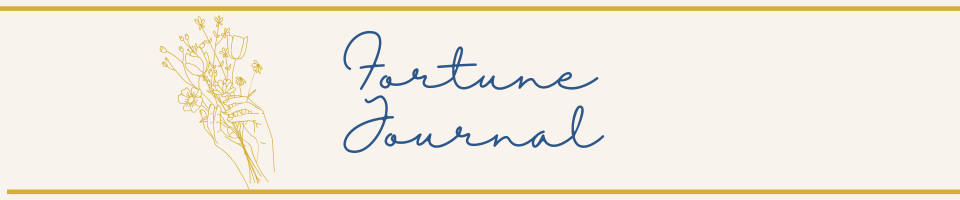毎年1月に行われる「十日戎(とおかえびす)」は、商売繁盛や家内安全、金運アップを願って多くの人が参拝する伝統行事です。
関西を中心に広く親しまれており、「えべっさん」の愛称で親しまれている恵比寿神(えびす様)を祀るこの行事では、縁起物を買い求めるのが定番。
でも、ふと疑問に思いませんか?
「この縁起物、本当に運気が上がるの?」
「どれを選べば効果があるの?」
この記事では、そんな疑問にお答えすべく、十日戎で手に入る縁起物の種類・意味・風水的な考え方・選び方のポイントをわかりやすく解説します。
十日戎とは?なぜ縁起物を授かるのか
十日戎の基本情報
- 開催日:1月9日(宵戎)〜11日(残り福)※10日が本戎(ほんえびす)
- 主な神様:恵比寿神(商売繁盛の神)
- 主な地域:西宮神社(兵庫)、今宮戎神社(大阪)、堀川戎神社(京都)など
なぜ縁起物が重要?
「えべっさん」は、参拝だけでなく縁起物を授かること自体が開運行為とされています。
風水でも、運の流れは“形あるもの”で引き寄せるという考え方があり、縁起物を家やお店に飾ることでエネルギーの流れが変わるといわれています。
十日戎は、基本的に関西以西で広まっているといえる行事です。毎年、えびす様に商売繁盛を祈願して神社でお祭りをおこなっており、関西では100万を超える人が集まることもあるのだとか。
【種類別】十日戎の縁起物と意味まとめ
1. 福笹(ふくざさ)
特徴:笹の葉に小判や米俵などの飾りをつける
笹は成長が早く、枯れにくいことから「繁栄」の象徴。
神社で配られ、他の縁起物を“福笹に取り付けて”持ち帰るのが一般的です。
2. 小判(こばん)
意味:金運・商売繁盛の象徴
黄金色のきらびやかな見た目が、財のエネルギーを呼び込みます。
3. 米俵(こめだわら)
意味:五穀豊穣・家内安全
米は「食」と「財」を兼ねた幸運の象徴。事業の安定と発展を祈る人に人気です。
4. 鯛(たい)
意味:「めでたい」に通じる語呂合わせ
風水では赤い色が邪気払い・活力の象徴とされ、家の西側に飾ると金運アップに◎
5. 熊手(くまで)
意味:福を「かき集める」道具として人気
商売繁盛・人脈運・幸運を一気に呼び込みたい人におすすめです。
6. 大福帳(だいふくちょう)
意味:昔の帳簿。多くのお客様との「ご縁」を意味します。
人脈運や取引運を高めたい事業主向けの縁起物です。
7. 船・宝船(たからぶね)
意味:七福神の乗り物。運の“流れ”を象徴
風水的には「財の循環」を促し、滞っていた運気の動きが活性化します。
スピリチュアル視点|縁起物の“本当の効果”とは?
縁起物は「願いの器」
風水や占いでは、縁起物はただの飾りではなく、運を宿す“器”として考えられます。
ただし、「持っている=自動的に願いが叶う」わけではありません。
願いを込めて選び、飾り、行動に移すことで初めて“開運”が動き出すのです。
願いが叶った人の共通点
- 縁起物を選ぶとき、「どんな未来を叶えたいか」を明確にしている
- 毎年新しい縁起物に更新して、感謝と祈りを忘れない
- 飾る場所を意識している(例:熊手は玄関付近、鯛は西側、小判は金庫の上など)
縁起物の選び方と飾り方【2025年版】
選び方のポイント
- 願いに合ったモチーフを選ぶ
・金運 → 小判
・商売繁盛 → 熊手
・人間関係 → 大福帳 - 見た瞬間「これ!」と思うものを信じる
→ 波動やエネルギーを直感で感じ取ることも大切です。 - できれば福娘(神社の巫女)から授かる
→ ご利益やエネルギーの“受け取り方”が違うとも言われます。
飾り方のコツ
- 清潔な場所に飾る(ホコリはNG)
- 願い事を書いた紙を近くに置くのも◎
- 毎年1月に「感謝して手放し、新しいものに更新」するのが理想
よくある疑問Q&A
Q. 去年の縁起物はどうすればいい?
A. 年明けに神社へ持参し、「お焚き上げ」してもらいましょう。
古い運気を浄化する意味があります。
Q. 複数の縁起物を選んでもOK?
A. OKです。むしろ願いごとに応じて複数持つ人も多いです。
ただし、欲張りすぎず、意味を理解して選ぶことが大切です。
まとめ|十日戎の縁起物で願いを“本当に”叶えるために
「本当に叶うの?」と疑う前に、まずは縁起物に自分の想いを込めて、信じてみること。
そして、行動を起こすことが開運の第一歩です。
縁起物選びのポイントおさらい
- 願いに合った種類を選ぶ
- 清潔な場所に飾る
- 感謝の気持ちを持って手放す
- 毎年更新して、運の流れを止めない
願いは「行動」と「信念」で育つもの。
十日戎の縁起物が、あなたの願いを引き寄せる大きなきっかけとなりますように。